運動が得意な人や、絵が上手い人を見ると「最初からセンスがある」と感じることがあります。
けれども実際はどうでしょうか。センスは本当に生まれつきのものなのか、それとも後天的に育つものなのか。今回は「真似」「師匠の一言」「興味と環境」という3つの視点から考えてみます。
芸術は「真似」から始まる
美術の時間に模写をやった経験がある人も多いはずです。線を追いかけて描くうちに、絵の構図やバランスが自然に身につきます。
音楽の世界でも同じで、ギターを始めた人なら「耳コピ」から入るのが定番です。好きな曲を何度も聴いて真似することで、リズム感や音感が体に染み込んでいきます。
実際に、ビートルズや桑田佳祐、ギタリストのCharなど有名なミュージシャンも「最初はコピーからだった」と口を揃えています。
真似を繰り返すうちに、自分の癖や感覚がにじみ出て、やがて“個性”と呼ばれるものになるのです。
師匠の一言が才能を開花させることもある
NHK大河ドラマ『べらぼう』では、片岡鶴太郎演じる鳥山石燕(とりやませきえん)が、染谷将太演じる喜多川歌麿に「お前には見えるはずだ」と語りかける場面がありました。
史実としてどこまで正確かは分かりませんが、このエピソードは「才能が師の一言によって一気に花開くことがある」という象徴的なシーンとして描かれています。
実際に多くの芸術家が「誰かに言われた一言で目が覚めた」「そこから本気で打ち込めるようになった」と語ります。
天才が突然生まれるのではなく、真似と努力の積み重ねに“きっかけ”が重なったときに爆発するのかもしれません。
興味と環境の力 ― 岡本太郎の例
岡本太郎は「芸術は爆発だ!」で知られる日本を代表する芸術家です。
彼は芸術一家に生まれ、幼少期から表現に囲まれて育ちました。さらにパリ留学で前衛芸術に触れ、帰国後は「太陽の塔」など独自の作品で時代を切り開きました。
岡本の場合は環境が後押しになりましたが、必ずしも家庭が芸術的である必要はありません。
大事なのは「やってみたい」という興味と、それを続けられる環境や機会です。資金や学ぶ場があれば、誰にでも道は開けます。
まとめ ― センスの正体とは?
芸術も運動も、最初の一歩は「真似」。
そこから興味を持ち続け、模倣を繰り返し、師や環境から刺激を受けることで、自分だけの表現へと育っていきます。
運動は「正しさ」を磨く世界。
芸術は「自分らしさ」を探す世界。
そう考えると、「センス」とは生まれつきのものではなく、
興味 × 模倣 × 継続 × きっかけ(人や環境) が掛け合わさった結果だと言えるでしょう。
👉 読者への問いかけ
「あなたが真似から始めて夢中になったことは何ですか?」
「だから今日からでも、好きなものを真似してみませんか?」
そして、もしお子さんが夢中で何かを真似している姿を見かけたら――
その時間こそが、未来の才能を育てているのかもしれません。ぜひ応援してあげてください。

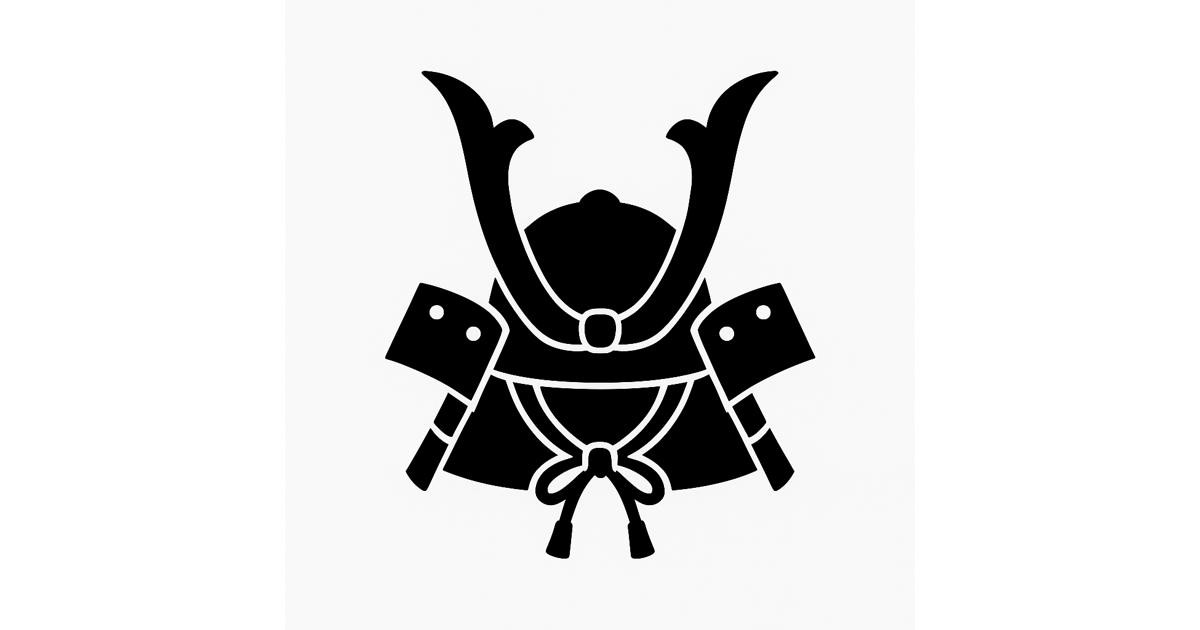
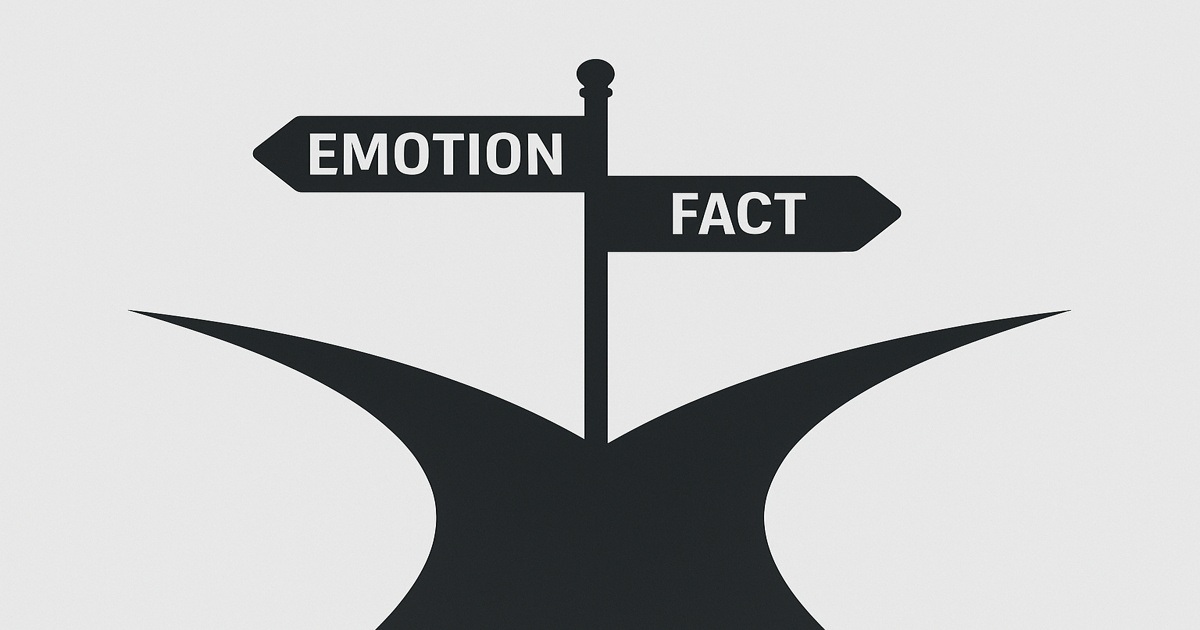
コメント