中学のときの級長って、だいたい成績がいい子とか、先生に信頼されてる子が自然に選ばれていた気がします。「こいつに任せればいいや」っていう雰囲気で、わりとあっさり決まってた。
でも、高校に入ったばかりの頃。まだ誰が誰なのかもよく分からない中で、級長を決める場面になると、なぜか「こいつでいいよな」って空気が流れる。そんな感覚、ありませんでしたか?
あれって不思議ですよね。誰かが強く推すわけでもないのに、みんなが納得してしまう。まるで、その人に「任せても大丈夫」と思わせる何かがあるような——今回はそんな話です。
中学では「見える評価」で選ばれる
中学の級長選びは、比較的はっきりしていました。通知表の評価や、提出物の丁寧さ、先生の評価がわかりやすく反映される感じ。
いわば、「安心と信頼の優等生」。ちょっと無理してでもがんばるタイプで、親も先生も安心できる。でもそのぶん、本人にとってはプレッシャーもあったでしょうし、「自分でやりたいからやる」というよりは「まかされたからやる」ことが多かったようにも思います。
高校では「空気」で選ばれる
高校に入ると、状況は少し変わります。
入学して間もない時期、クラス替えで誰がどんな人かもまだわからない中で、級長を選ぶとき——なぜか「あいつでいいんじゃね?」という空気になる。
これが本当に不思議です。
とくに立候補したわけでもない、派手な存在でもない。でも、「なんか大丈夫そう」な人がいて、いつのまにかその人に決まっている。まわりも「あいつなら間違いない」と、どこか納得している。
こういうのを見ると、人間ってすごいなと思います。まだよく知らない相手なのに、「この人は大丈夫」と感じるセンサーが、意外と正確に働いているんですね。
「人徳」って、にじみ出るものなのかもしれない
高校で級長に選ばれるような人って、決して目立つタイプではないことも多い。でも、落ち着いていて、人の話をちゃんと聞いて、誰にでも同じように接している。そういう空気をまとってる。
そう考えると、「人徳」ってにじみ出るものなんだなと思います。
教科書的なリーダー像ではなく、「この人がいると安心する」という空気感。無理に仕切らず、だけど必要なときは自然と一歩前に出てくれる——そんな人には、何か“根っこ”がある。
声のトーンだったり、姿勢だったり、目の動きだったり。小さな部分がじわじわと信頼につながっていく。それがたぶん、「人徳」ってやつの正体なんじゃないかと思います。
社会に出ても同じことが起きている
この感覚って、大人になっても変わらないんですよね。
会社でも、町内会でも、ボランティアの場でも。「なんとなくあの人がいいよね」と感じる人が、結局まわりから信頼されていたりする。
その理由は、やっぱり「見えない部分」で決まることが多い。
- 声を荒げない
- 話を最後まで聞いてくれる
- 誰かの陰口を言わない
- 誰に対しても変わらない対応ができる
こういう人に、「任せても大丈夫」という安心感が生まれるのは、高校の級長選びと同じです。
結び:人徳は、日常の中からにじみ出る
結局、「この人に任せたい」と思われるかどうかは、毎日の小さな行動の積み重ね。
大きなことをしなくてもいい。むしろ、静かに、地に足のついた態度のなかに、その人の“信頼される力”がにじみ出てくる。
高校の級長に「なんとなく」選ばれた人たちは、それを無意識に持っていたのかもしれませんね。
追伸(読者への一言)
あなたのクラスにも、そういう「なんとなく安心できる人」がいませんでしたか?
そう感じた人がいたなら、たぶんあなたの“人を見る目”も、けっこう確かです。
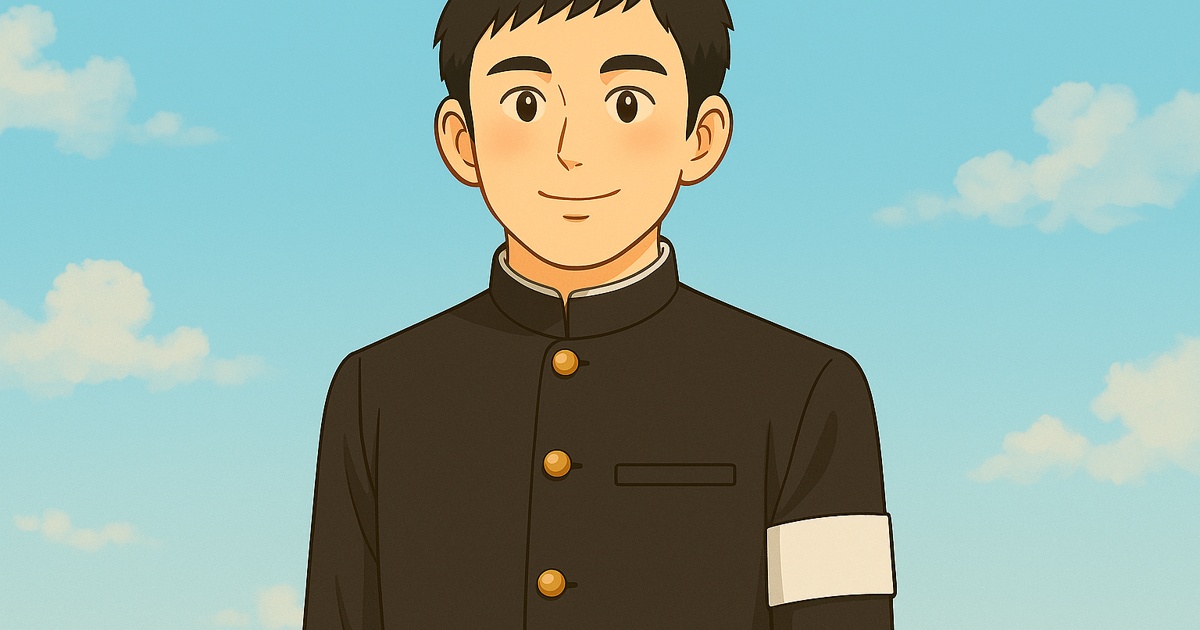


コメント