【導入】
ある市長の話を、最近ニュースで目にした。
学歴について疑念が持たれ、当初は辞職の意向を示していたが、最終的には一転して続投を宣言。
「なぜ?」「どうしてそんな行動を?」という世間の声が相次いだ。
その様子を見ていて、あるニュースの出来事が頭に浮かんだ。
■ 自分の屋敷にゴミを集めて正当化する人
それは、ニュースでよく見る“ごみ屋敷”の住人だ。
家の周りは物であふれ、通行人が眉をひそめても、本人は「これは大事なものなんだ」と言い張っていた。
行政が動こうとすれば「勝手に捨てるな!」と怒鳴り、家族の助言にも耳を貸さなかった。
あの市長の姿に、その人と重なるものを感じた。
どちらも共通しているのは、「外からの声を受け入れられない」という点だ。
正しいかどうかより、自分の考えを守り通すことが優先されてしまう。
■ 間違いよりも“誤魔化し”が信用を失わせる
人は誰でも間違える。
ミスや勘違い、失敗をしてしまうことはある。
でも、そこからどう向き合うかで、その人の信頼が決まる。
この市長の行動に、私たちがモヤモヤするのは、
「間違いを認めないこと」や「誤魔化しで押し通す姿勢」にある。
実は、これは私たちの身の回りにもよくあることだ。
職場で自分の非を認めない上司、家族の指摘にムキになって反論する誰か。
あるいは、過去の自分自身。
■ “あの人”にイライラしていた人のために
もし今、あなたの周りにも「どうしてあの人は謝らないんだろう」と感じる誰かがいたら、
この話が少し役に立つかもしれない。
人が意地を張ってしまうのは、自分を守るため。
プライドや恐れ、過去のこだわり――それらを崩すのが怖いからだ。
それを理解することで、少しだけ気持ちがラクになることもある。
相手を許せなくても、距離の取り方や見方が変わるだけで、心の負担が減る場合がある。
■ 自分自身も“正当化の罠”にハマることがある
人のふり見て、わがふり直せ。
実は、自分の中にも小さな“ごみ屋敷”のような部分がないとは言い切れない。
「これは必要なことなんだ」と言い訳して続けている習慣。
「間違いかも」と思っても認めたくない過去。
そんなものを、自分の中にそっと置いていないだろうか。
私たちは皆、少しずつ“正当化”をして生きている。
だからこそ、あの市長の話は“他人事”ではない気がした。
■ 信頼は、自分で主張するものではない
信頼とは、「私を信じてください」と言って得られるものではない。
相手が自然にそう思える行動の積み重ねで、初めて築かれるものだ。
「私は悪くない」「正しいのは私だ」と言い張る人ほど、信頼から遠ざかっていく。
それに気づかないまま、誰もいなくなってから後悔しても、もう遅いのかもしれない。
■ 信念とわがままの違いを、どこで分けるか
もちろん、誰にでも「譲れない思い」はある。
だけどそれは、人様に迷惑をかけない形で貫いてこそ、“信念”と呼べるものだと思う。
他人の信頼を犠牲にしてまで押し通すのは、もはや“ただのわがまま”なのかもしれない。
本当に信念を持つ人とは、まわりを巻き込まず、静かに、誠実に、それを守り続けている人なのだと思う。
■ 結びに:正しさより、誠実さを
この市長がどうなるのかはわからない。
でも、私たち自身はどうありたいか。
間違いを認め、素直に謝り、誠実に向き合う人でいたいと思う。
それは勇気のいることだけど、信頼される人になるためには欠かせない一歩だ。
誰かにとって、この話が“気づき”や“心の整理”のヒントになれば嬉しい。
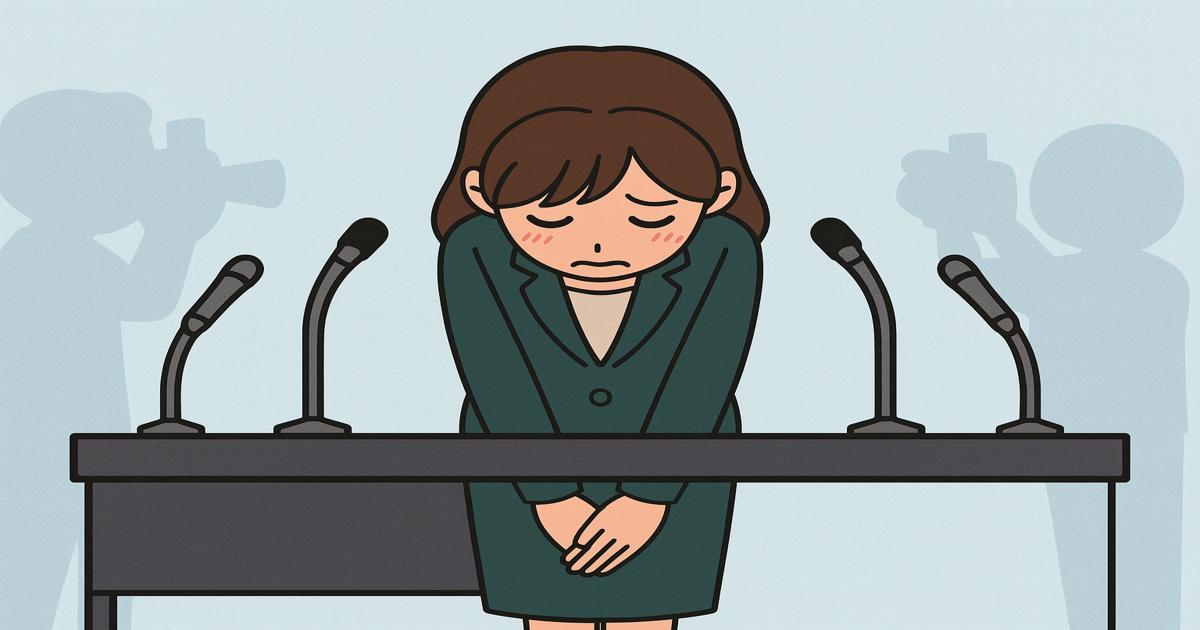


コメント