あの頃の圧倒的存在感
学生時代、必ずクラスやチームに一人はいました。
「エースで4番」と呼ばれる存在。
力強くボールを飛ばし、走れば誰よりも速く、ジャンプすれば高く舞う。
投げても打っても守っても、一人で試合を支配してしまうような万能型。
周囲から見れば、まさに「無敵」でした。
体力+運動神経の相乗効果
なぜ彼らはそんなにすごく見えるのか。
- 筋力、走力、ジャンプ力の三拍子が揃っている
- それに加えて運動神経がずば抜けている
- だから自然とエースで4番を任される
こうした総合力が一人の中に収まっていると、チームメイトからは「次元が違う」と見えてしまいます。
決定的な場面で結果を出し続けることで、自信と風格までまとい、「絶対に敵わない」と思わせる雰囲気をつくりあげていたのでしょう。
イメージどおりに動ける力
さらに不思議なのは、イメージどおりに身体を動かせること。
これは生まれつきの才能というよりも、観察と模倣の積み重ねに秘密があるのかもしれません。
子どもは、親や兄弟、友達のかっこいい動きをじっと凝視し、集中して観察します。
そして真似してみる。
自分の子どもを見ていても、同じように「飲み込みが早い」と感じる瞬間がありました。観察してから試し、それなりの動きをしてしまう。
つまり運動神経の良さの一部は、探究心と模倣力から生まれる「学習の産物」でもあるようです。
環境がつくる差
ただし、誰もが同じように成長できるわけではありません。
興味を持ったことに集中できる環境があるかどうか。
親が「やってみなさい」と挑戦させるのか、「危ないからやめなさい」と止めるのか。
そうした親の考え方やスキルが、子どもの学びに大きく影響します。
そして、正直に言えば——
「金持ちの余裕のよっちゃん」な家庭なら、道具も環境もそろっている。
そりゃあ強くなるよな、と皮肉りたくなることもあります。
大人になって気づくこと
子どもの頃はただ「天才」と見えていたエースで4番。
でも大人になって振り返ると、そこには努力の積み重ねがあり、恵まれた環境の影響があり、そして時には家庭の経済力すら関係していたことに気づきます。
だからこそ今思うのです。
「あの頃の無敵に見えた存在も、結局は努力や環境の産物だったんだな」と。
親ができる3つの工夫
最後に、子どもの「運動神経」や「身体の使い方」を伸ばすために、親ができる工夫を3つだけ。
- 観察の時間を与える
じっと見ているときに中断させず、集中を尊重する。観察と模倣は学びの原点。 - 「やってみなさい」と機会をつくる
危険を理由に止めるよりも、安全に挑戦できる方法を工夫する。経験が自信を育てる。 - 興味を伸ばせる環境を用意する
ボールでも縄跳びでも、自転車でも。すぐに手に取れる環境が探究心を育てる。
こうした小さな積み重ねが、子どもの可能性を大きく広げます。
そしてその姿を見ていると、「エースで4番」の秘密が、少しわかる気がするのです。

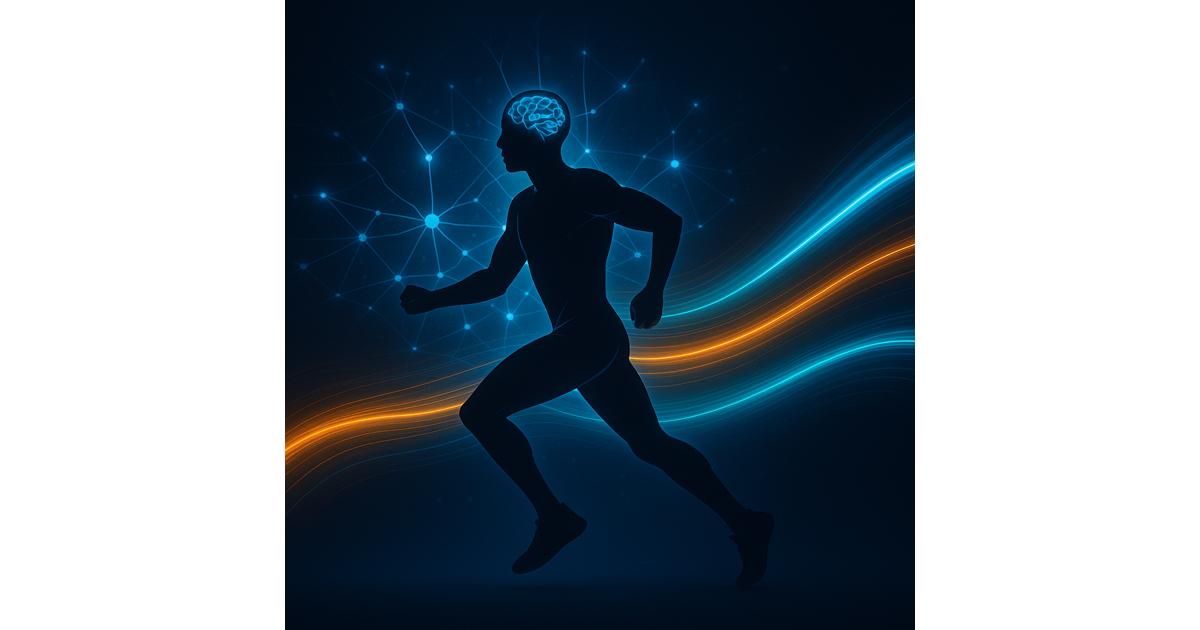
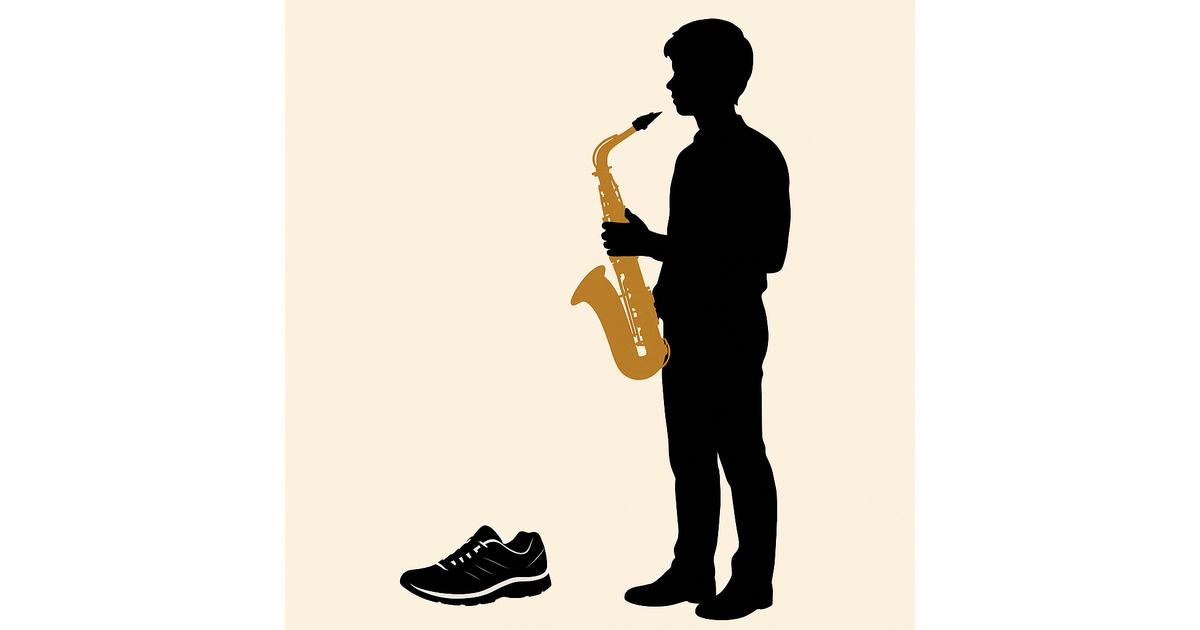
コメント