NHKのドラマ『舟を編む』を観た。辞書作りに情熱をかける人たちの物語。
これが想像以上に面白くて、つい見入ってしまった。
考えてみれば、最近はすっかり辞書を引かなくなった。
スマホやパソコンがあるから、わからない言葉が出てきてもサッと検索すれば済む。
「辞書を引く」なんて、もう昔の話だと思っていた。
でも、思い出す。
小学生のころ、そして中学・高校時代。
国語辞典や漢和辞典を机の上に広げて、「これ、なんて読むんだ?」とページをめくった日々。
率直?恭賀新年? 読めない漢字だらけだったあの頃
「率直」「恭賀新年」なんて言葉、初めて見たときは意味も読み方も分からなかった。
テレビや歌の歌詞で流れてくる言葉――
コブクロの「蕾(つぼみ)」、
「掴む(つかむ)」という字の形、
「瑠璃色(るりいろ)」ってどんな色?
「寂寞(せきばく)」なんて、読めもしないし書けるわけがない。
「泥濘(ぬかるみ)」は今でも難しい。
そんなとき、辞書を引いた。
調べて「なるほど」と思ったあと、不思議と目が隣の単語へと移っていく。
目的の言葉を見つけたはずなのに、その周りの言葉にもつい目が止まり、読みふけってしまう。
辞書って、そういうものだった。
スマホ検索にはない“寄り道”の楽しさ
現代の検索は便利だ。
知りたい言葉を打ち込めば、一瞬で意味が表示される。読み方も用例も教えてくれる。
だけど、そこには「偶然の出会い」がない。
辞書には、それがある。
隣の言葉、似たような言葉、なぜか気になる言葉。
目的とは関係ないのに、なぜか心を惹かれて読んでしまう。
あれは、まるで散歩のような感覚だった。
どこへ向かうか決めてないのに、気づけばいろんな景色を見て帰ってくる。
辞書を開くという、ちょっとした贅沢
辞書って、知識の詰まった本なのに、どこか温かい。
作る人の手間や思いが、ぎゅっと詰まっているからだろうか。
『舟を編む』を観て、そんなことを思い出した。
言葉って、誰かが大切に選び、並べてくれているんだ。
辞書って、その積み重ねそのものなんだなと。
スマホ全盛の今でも、たまには紙の辞書を開いてみるのも悪くない。
知ってるようで知らない言葉、
読めないけど響きの美しい漢字、
そして、読むつもりじゃなかった隣の言葉たちに、また出会えるかもしれない。

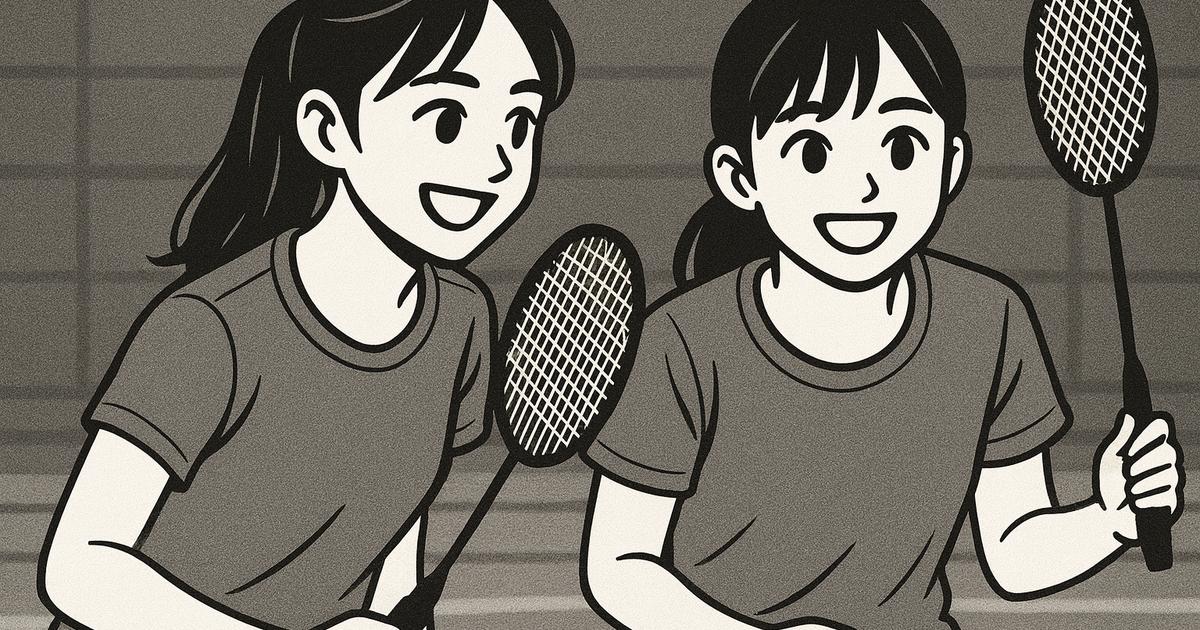
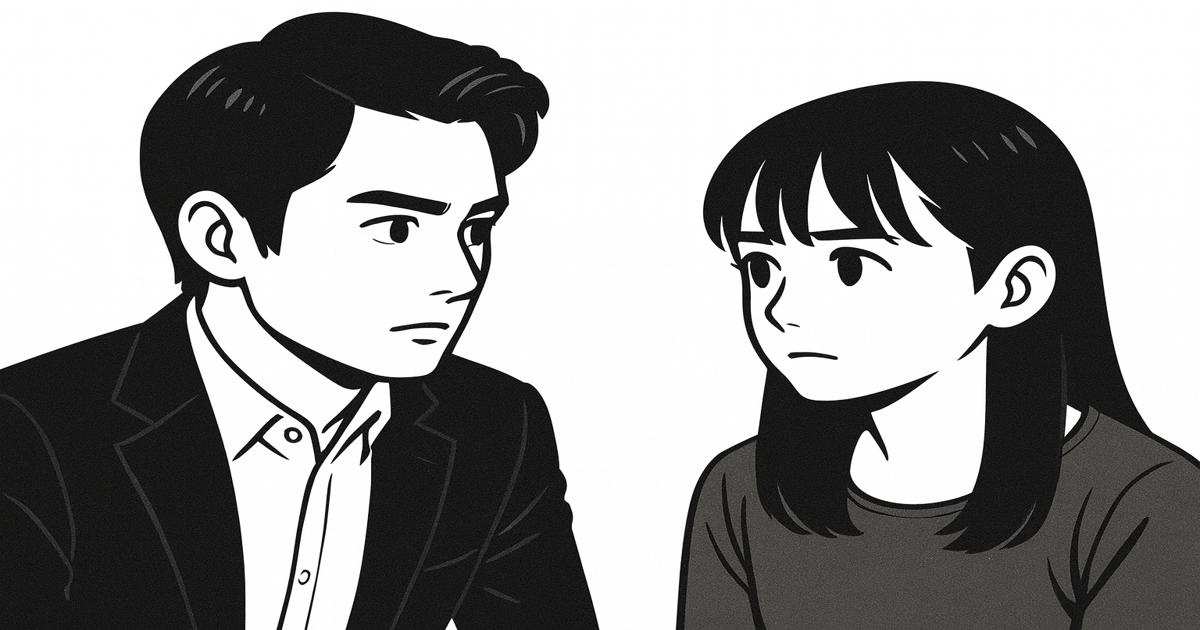
コメント