■ はじめに:知らんかった
私が飛行機に乗ったのは一往復だけ。成田からロサンゼルスへ。
行きは十数時間、帰りは偏西風のおかげで少し短く感じたのを覚えています。
もちろん座席はエコノミー。ファーストクラスやビジネスクラスのことなど、まったく縁のない世界でした。
そんな私が最近知ったのが「ファーストクラス理論」。知らんかった。
どうやら、エコノミーが安く乗れるのは、ファーストクラスに座る人が高額を払っているかららしいのです。
■ ファーストクラス理論とは
飛行機の座席は大きく分けてエコノミー、プレミアムエコノミー、ビジネス、そしてファーストクラス。
最上級のファーストは、専用空間と豪華なサービスがつき、料金も桁違いです。
航空会社にとっては大きな収益源であり、その利益があるからこそ、エコノミーを安く提供できる。
言い換えれば──
「一部の人が高く払うことで、多くの人が安く利用できる」
これがファーストクラス理論です。
■ ホテルやコンサートも同じ構造
考えてみれば、ホテルも同じです。
一泊数十万円のスイートルームがあるから、シングルが数千円で泊まれる。閑散期には原価割れのような料金も可能です。
コンサートや舞台もそう。
最前列のVIP席が数万円することで、2階席が数千円で提供できる。
新幹線では、グリーン車やグランクラスの高額料金が普通車の割安切符を支えている。
「高い席があるから、安い席もある」──これもファーストクラス理論です。
■ 食品・飲食業界の“目玉商品”
もっと身近な例もあります。
スーパーの「玉子1パック98円」や、居酒屋の「生ビール最初の一杯100円」。
あれは原価割れ、もしくはほぼ利益なし。
でも、それを目当てに客が来て、他の商品やサイドメニューで利益を取る仕組みです。
「安さで呼び込む商品」と「利益を出す商品」を組み合わせる。
これもまたファーストクラス理論の一種です。
■ 影の部分──中小店の厳しさ
ただし、この仕組みには影の部分もあります。
大手スーパーは大量仕入れができるから、玉子を98円で売っても他で回収できる。
でも小さなスーパーは仕入れ自体が高いので、同じ値段では出せない。
「なんであの店より高いの?」と客に思われ、「高い店」というイメージを持たれてしまう。
飲食店でも同じで、大手チェーンはビール100円をエサにできるけれど、個人店はそうはいかない。
結果として中小が苦しくなり、潰れていく現実があります。
便利さの裏で、こうした競争があることも忘れてはいけません。
■ まとめ
たった一往復の飛行機体験から知った「ファーストクラス理論」。
これは飛行機に限らず、ホテル、コンサート、新幹線、スーパーや飲食店にまで広がる「価格の不思議」でした。
- 誰かが高く払うから、誰かが安く利用できる。
- 高額商品と低価格商品が組み合わさることで全体が成り立っている。
- ただし、大手が強い分、中小が割を食う現実もある。
世の中の仕組みは、表から見える値札以上に複雑で、誰かの支え合いで成り立っています。
エコノミーしか知らない私にとっても、この気づきは大きな学びでした。

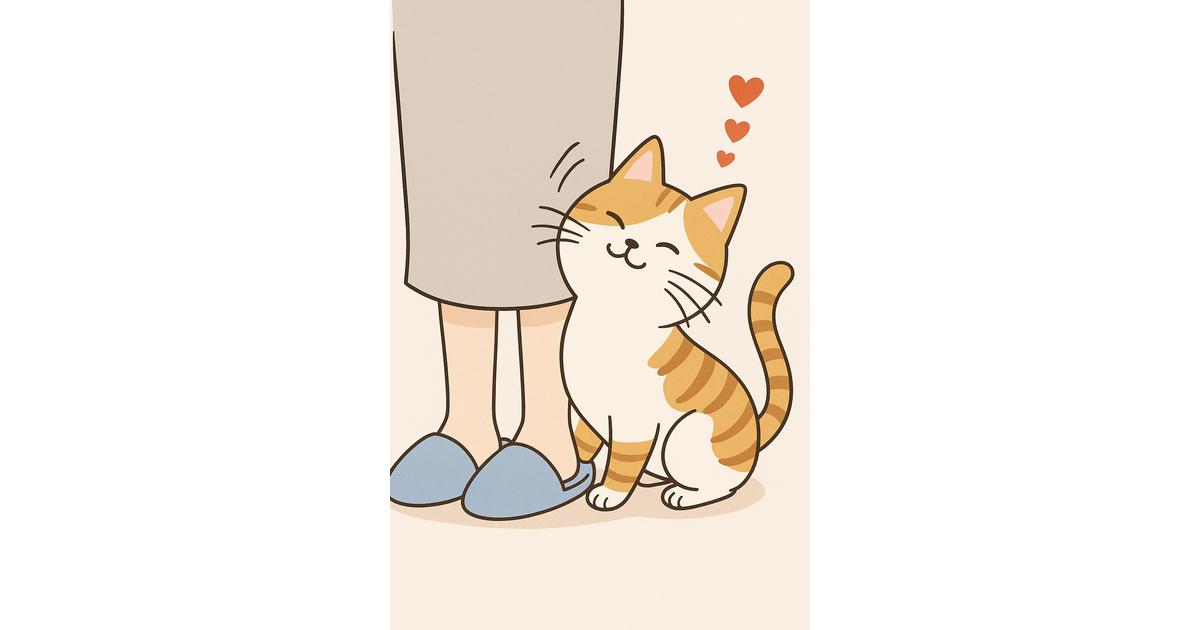

コメント