定年後に夫婦で過ごす時間が増えてきて、こんなことを思うようになった。
私たち夫婦は、ほとんど喧嘩をしない。
だからこそ気づいたのかもしれない。
「白黒つけたがると、かえってしんどくなることもあるなあ」と。
何か小さなすれ違いがあったときでも、
「どっちが悪いか」をはっきりさせようとすると、
相手を責めるような空気が生まれやすい。
それよりも、「まあ、どっちでもええか」で流したほうが、心地よく過ごせる。
■ 白か黒かじゃなく、“グレー”でいいこともある
日本人は昔から、はっきり白黒つけるのを避けるところがある。
それを「曖昧だ」「はっきり言え」と言う人もいるけど、
人間関係においては、その“グレーゾーン”が役立つことがある。
0か100じゃなく、「まあ50くらいで」とおさめることで
ケンカにならなかったり、うまく落としどころが見つかったりする。
実際、欧米のように自己主張が強い文化では、
「私はこう思う!」が大事だけど、
日本では「まあまあでいいじゃない」が場をなごませる。
■ 行間を読む文化、察するチカラ
日本語って面白い。
言葉にしなくても、伝わることを前提にしている部分がある。
「ちょっと…ね」
「いや、別に…」
こういう言葉の“間”にある空気や感情を読み取るのが、日本人の得意技。
欧米の文化では「言ってくれなきゃ分からない」で済むけど、
日本では「言わなくても分かってくれないと困る」となることも。
でも、これって実はすごい能力かもしれない。
相手の立場に立って、表情や声の調子、タイミングで“気持ち”を読む。
まさに「察するチカラ」だ。
■ 「いい塩梅にしてください」という言葉に癒された
内藤いづみさんという医師がいる。
終末期医療の現場で、患者さんや家族と向き合ってきた方だ。
ある対談で、こんな言葉を紹介されていた。
「先生、いい塩梅でおねげえしやす」(お願いします)
薬を強くしても、手術をしても、完璧にはならない。
それでも、苦しみすぎず、ほどよい状態でいられるように。
そんな願いがこもった言葉だった。
この「いい塩梅(あんばい)」って、人間関係にも言える気がする。
言いすぎない、押しすぎない。
無理をしない、我慢しすぎない。
お互いの“ちょうどいい”を探すこと。
■ 察するチカラは、決して弱さじゃない
「はっきり言わない」「白黒つけない」というのは、
決して曖昧な逃げではなく、
むしろ「大人の知恵」なのかもしれない。
柔らかくて、しなやかで、
ぶつからずにすっと交わせる力。
これからの時代、
世界が分断されがちな今こそ、
日本人がずっと大事にしてきた“察する文化”が見直されるかもしれない。
今日も、田んぼ道を歩きながら思った。
「いい塩梅にしてくんない」
この言葉、しみじみといいなあ。
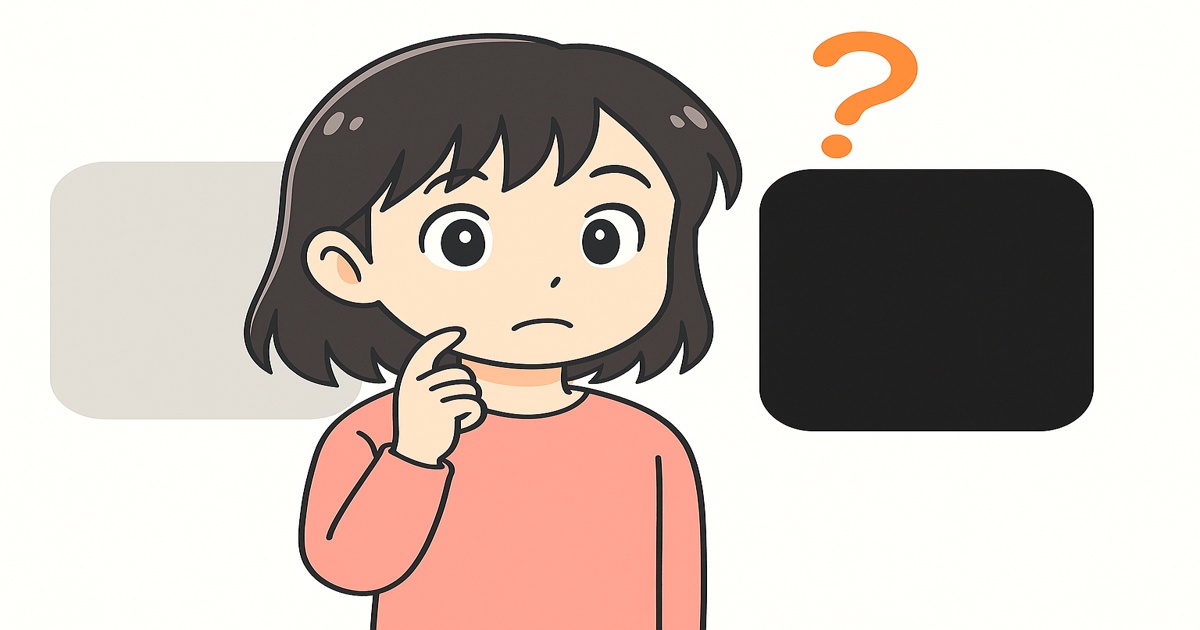

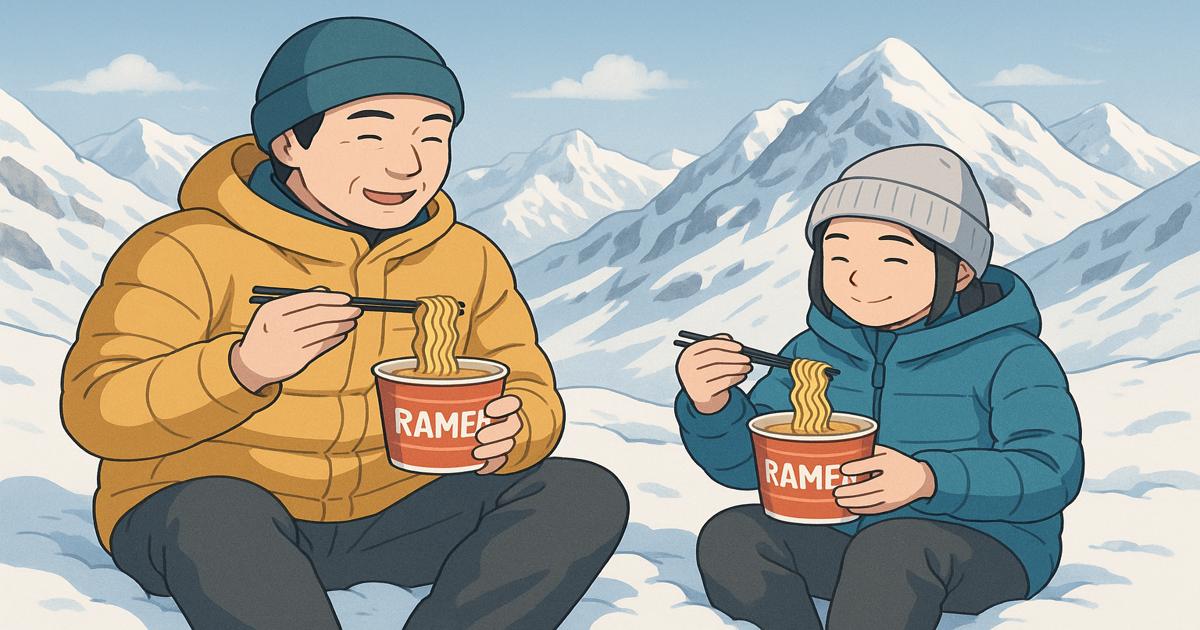
コメント