序章:スポーツ万能じゃない現実
学生時代、運動神経のいい奴はいつも目立っていた。体育の時間でも、部活でも、行事でも。クラスのヒーローはたいてい「走れる」「跳べる」「投げられる」人間だった。
でも実際には、運動が苦手な奴のほうが多い。残念ながら、自分もその一人だった。
いや、正確に言えば「半分だけ」できるタイプだった。野球はそこそこ自信があったが、それ以外は全然ダメ。だからこそ、できないことの悔しさを強烈に覚えている。
(毒)体育の授業なんて、エース気取りの奴に見下されてイライラする場でもあった。
中途半端なやつの苦しさ
もし何もかも苦手なら、諦めもつく。「自分は運動ダメだから」と笑い飛ばせるだろう。
でも一部だけできると、周囲から「他もできて当然」と思われる。
野球ができるからといって、バスケでドリブルが上手いわけじゃないし、跳び箱を軽々と飛べるわけでもない。なまじ一つできたせいで、できない種目では余計に悔しさが増した。
(毒)「なんで跳び箱くらいできねえんだよ」と言われる筋合いはない。俺は野球選手志望であって、体操選手じゃない。
さらに厄介なのは、昔できたことが年齢とともに通用しなくなることだ。中学までは自信満々だった野球も、社会人になってから朝野球や地元チームに参加すると、まるで別人のように動けなかった。打てない、守れない、走れないの三拍子揃う。うまかった自分を見せたいとカッコつけても、現実は散々だった。あの瞬間、野球が少し嫌いになったのを覚えている。
苦手な奴はどう生きるか?
じゃあ、運動がダメな奴はどうすればいいのか。
答えはシンプルだ。運動以外の領域で戦えばいい。
文化部に入るもよし、音楽や吹奏楽に打ち込むもよし、絵を描く、文章を書く、研究に没頭する――選択肢はいくらでもある。
むしろ「運動神経オンチ」だからこそ、自分の得意を真剣に探すきっかけになる。
今になって思うのは、音楽にもっと早く触れていればよかったということ。吹奏楽部に入っていたら、別の人生があったかもしれない。あの頃は「運動がすべて」と思い込んでいたけれど、こだわりすぎて逆に苦しくなっていたのだ。
(毒)体育祭でリレーのスターになった奴が、社会に出てからもスターでいるとは限らない。
読後感:エースで4番の逆サイドに立って
運動が苦手でも、別の場所で生きる道はある。
むしろ「苦手だった悔しさ」が努力や探究心の原動力になることもある。
振り返れば、あの頃の“できない自分”は、無駄じゃなかった。
エースで4番の輝きはなかったけれど、逆サイドに立ったからこそ見えた景色がある。
そして今は思う。運動が苦手な奴は、苦手を抱えたままでも十分に生きられる、と。
得意がなくても、諦めなければ別のフィールドが見えてくるのだ。
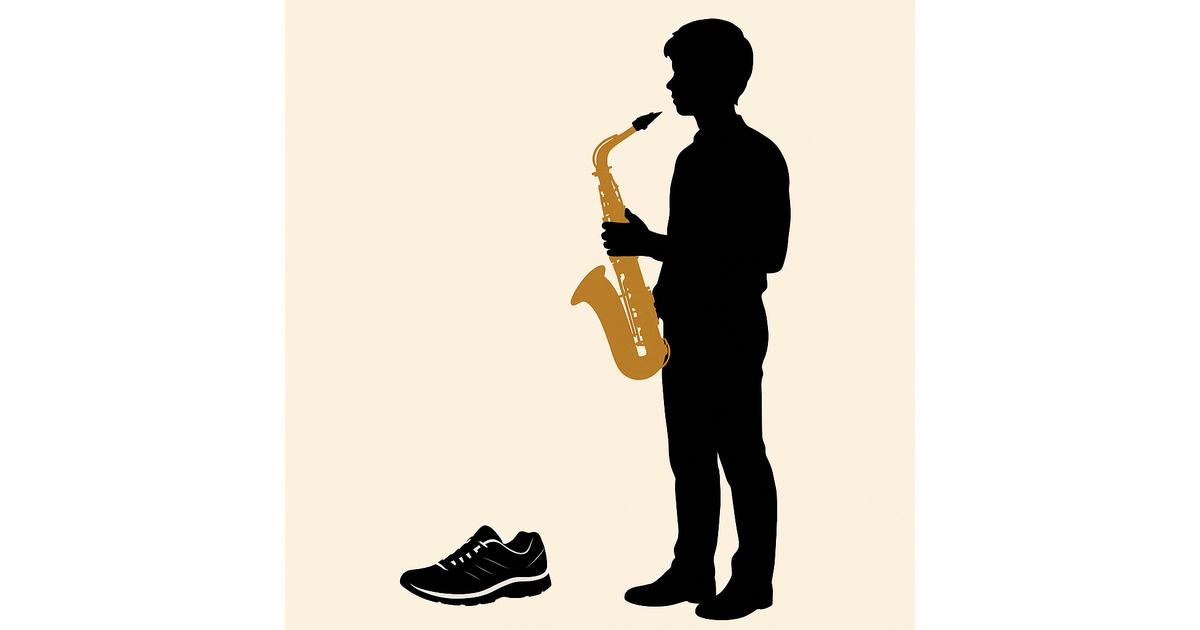


コメント