本文
「昔の人たちは、どうやって情報を得ていたんだろう?」
スマホひとつで何でも調べられる今の時代。
そんな便利さに慣れてくると、ふと考えることがあります。
ネットもSNSもなかった頃、人はどうやって知恵を得て、生きる力を身につけてきたのか――。
おそらくその答えは、「人に会うこと」だったと思うのです。
長老からの教え。知恵は人の中にあった
昔の地域社会では、年長者、いわゆる“長老”たちが大切な知恵の宝庫でした。
農作業のタイミング、自然の変化の読み方、道具の扱い方、そして地域の歴史や風習まで。
それらは本ではなく、「人の口」から「人の耳」へと伝わっていきました。
「この風が吹いたら、もう田んぼに入ってはいかんぞ」
「カラスが鳴いたら、明日は天気が崩れるかもしれん」
こういった暮らしの中の知恵は、日々の会話や作業の合間に自然と身についていくものでした。
机に向かって学ぶのではなく、人と向かい合って学ぶ――それが当たり前のことだったのです。
町内会や寄り合いは“リアルな情報の場”だった
地域の寄り合い、町内会の集まり、さらには酒席も、情報交換の重要な場でした。
お祭りの打ち合わせや、ちょっとしたトラブルの話し合い。
誰が何を困っているか、どの家がどんな事情を抱えているか――
そういった“空気”のような情報が、日常の会話の中に溶け込んでいたのです。
こうした場で交わされる会話の中には、
「今すぐ役立つ情報」だけでなく、「あとからじわじわ効いてくる言葉」も多くありました。
書物や新聞もあった。でも一番は“人”
もちろん、昔から本や新聞といった文字による情報もありました。
町の掲示板、回覧板、地元の新聞など、地域の情報源として欠かせないものでした。
けれど、それらはあくまで補助的な存在。
実際には、人と人の対話の中から得られる“実感のある情報”が、一番信頼されていたように思います。
両学長の言葉にある「人に会うタイミング」
リベ大の両学長も、YouTubeでこんなことをよく話しています。
「これは、人に会うタイミングやな」
「悩んだときは、誰かに会って話してみると、流れが変わることがある」
まさにその通りだと思います。
人と会って、会話して、感じる。そこからしか得られないヒントがあるんです。
一見くだらない話も、じつは“気づきの種”になる
最近は、「会社の飲み会は時間のムダ」と言われることも増えました。
確かにそう感じる場面もあるでしょう。
でも、本当に“ムダ”なのでしょうか?
何気ない会話の中に、「自分がふだん考えない角度の話」がふっと出てくることがあります。
たとえ結論のない話でも、「なぜこの人はそう考えるのか?」という視点で見てみると、
人間関係や立場の違い、自分との考え方のズレに気づかされることも。
一見つまらない会話も、自分にとっての“観察と学びの場”になる。
だから、誘われた場にはあまり断らずに参加してみる。
そのひとつひとつが、いつか自分の中で“引き出し”になるかもしれません。
結局、学びは人の中にある
昔の人も、現代の僕たちも、結局は「人から学ぶ」のが一番早いのだと思います。
ネットで得られる情報は整理されていて便利だけれど、
人の体温を感じるような学びは、やっぱり“会ってこそ”生まれる。
尊敬できる人に会って、話を聞く。
その人の考え方や立ち居振る舞いを見て、自分の糧にする。
そして、今度は自分が誰かの役に立つ番になる――
そんな循環をつくっていけたら、人生はもっと面白くなると思います。


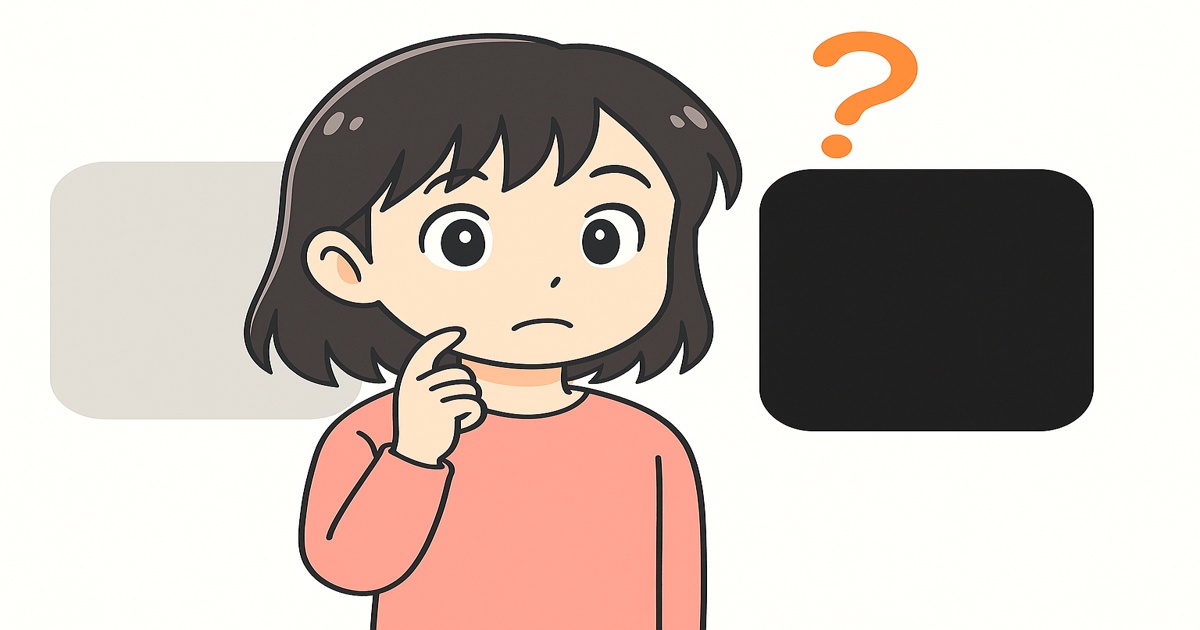
コメント