──極限の雪山が教えてくれた感覚の話
本文
はじめに
さんまさん司会のテレビ番組に、登山家の野口健さんと娘の絵子さんが出演していました。
彼らが語っていたのは、標高6,476メートルのメラピークでの体験です。そこは「においも音も、ほとんどしない世界」だったそうです。
植物も動物もいない、無菌に近い環境。
風は吹いているのに、花の香りも排気ガスも、何のにおいもしない。
その話を聞いて、私は思いました。
「においがないって、どういうことだろう?」
「そして、そんな場所で人は“何を欲しくなる”のだろう?」
雪山の極限環境──無臭の世界
標高6,000メートルを超える世界。
植物も生き物も育たない場所では、空気にほとんどにおいがありません。鼻に届く刺激がないのです。
私たちは普段、意識しなくても多くのにおいに囲まれています。
朝のコーヒー、通勤電車、夕食の支度、街の空気。
けれど、においが完全に消えると、
人は逆に「嗅覚が鋭くなったように感じる」ことがあるそうです。
健さんは、下山後に電車に乗った際、
周囲のにおいを強く感じすぎて、思わず注意されたと話していました。
それだけ嗅覚は“慣れ”に左右されやすく、
刺激がなくなることで、感覚が研ぎ澄まされるのかもしれません。
本能が選ぶ──即席ラーメンの話
さらに印象的だったのが、雪山での食事の話です。
「普段は絶対に食べないけれど、登山中はなぜか即席ラーメンが食べたくなる」
そう言って、親子でラーメンをすする話が紹介されていました。
冷え切った体に、熱々のスープ。
健さんは地上ではほとんど口にしないという「辛ラーメン」を、
雪山では毎朝食べていたそうです。寒さで体が冷え切っていたからでしょう。
空気が薄く、血行も悪くなり、指先がかじかむ。
そんな環境で体を温めるために必要なもの――
濃い塩分、油分、炭水化物。即席ラーメンには、それらがすべて詰まっています。
標高が高くなると、味覚や嗅覚も鈍くなると言われています。
そんな中で、体が本能的に「これが必要だ」と判断しているのかもしれません。
そして興味深いのは、
同じ場所にいても、人によって欲しくなるものが違うという点です。
体調や状態によって、「足りないもの」は人それぞれ。
体は、ちゃんと自分なりのサインを出しているのだと感じました。
感覚を研ぎ澄ますということ
この話を聞きながら、私は考えました。
私たちの五感――
視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚は、
日々の刺激や雑音に囲まれることで、
逆に「感じにくくなっている」のではないか、と。
感覚は、遮断されることで、かえって鋭くなることがあります。
無音の中で、小さな物音に気づく。
無臭の空間で、香りが際立つ。
暗闇の中で、触れた感触が豊かになる。
つまり、
五感を研ぎ澄ますには、刺激を増やすのではなく、
いったん減らしてみることが大切なのかもしれません。
五感を取り戻す、日常の小さな工夫
五感を意識するために、特別な道具や費用は必要ありません。
日常の中で、少し意識を向けるだけでも変化を感じる人は多いようです。
視覚
朝の散歩で、あえて色の少ない場所を歩いてみる。
「今日は何色に気づけるか」と意識するだけでも、風景の見え方が変わります。
聴覚
静かな時間に1分間、目を閉じて音に集中してみる。
鳥の声、風の音、遠くの車の音などが、自然と耳に入ってきます。
触覚
目を閉じて、コップやスマートフォンを触ってみる。
素材や温度の違いに、改めて気づくことがあります。
嗅覚
無香の空間で、ひとつの香りだけを意識して嗅いでみる。
食べ物の香りを、ゆっくり吸い込んでみるのも一つです。
味覚
ひと口ずつ、味を確かめながら食べてみる。
甘み、塩味、酸味のどれが強いかを意識するだけでも、印象は変わります。
調べてみると、わかること
五感を意識的に使うことについては、
「感覚を使って脳を活性化する方法」として紹介されていることも多いようです。
とくに、感覚に集中することが、
集中力や注意力を高める助けになると考えられています。
一般的には、
・記憶や集中への良い影響
・リラックスにつながる
・創造性や直感への気づき
などが挙げられることが多いようです。
「五感を鍛える」というより、
“自分を取り戻すための静かな習慣”と考えるほうが、しっくりくる気がします。
おわりに──体が教えてくれること
この話から、私が感じたのは、
「感覚を研ぎ澄ますには、まず“感じない時間”をつくること」
「人は、体で“本当に欲しいもの”を知っている」
ということでした。
ラーメンが食べたくなるのも、
においを強く感じたくなるのも、
体が「いま、これが必要だよ」と伝えているサインなのかもしれません。
散歩でも、静かな時間でも、短い瞑想でもいい。
そうした時間が、自分の感覚を信じる力につながっていく。
そしてその感覚は、
健康にも、心の落ち着きにも、日々の学びにも、
静かに影響していくのだと思います。
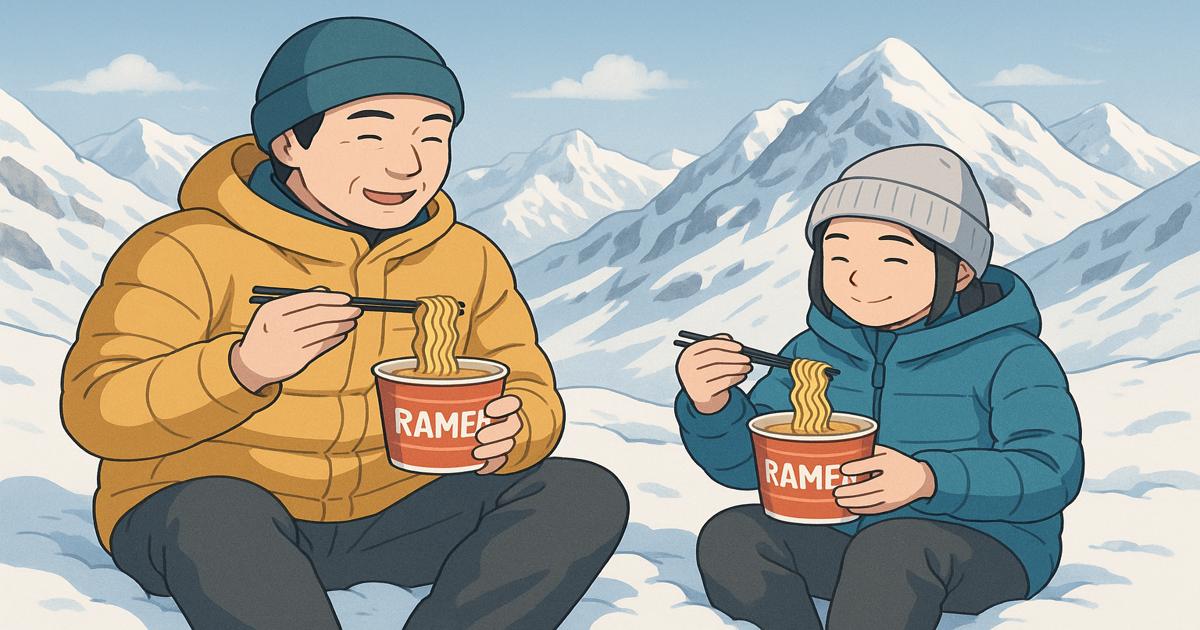
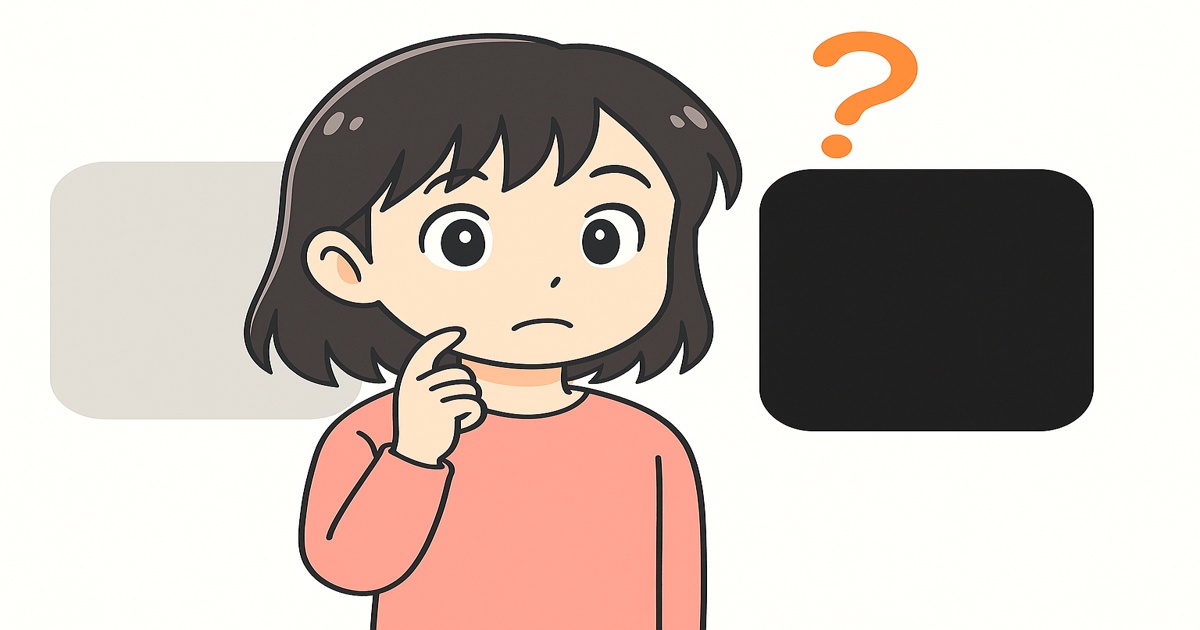

コメント