定年を迎え、仕事の第一線から離れてみて、あらためて思うことがある。
それは、健康を守るのは「医者」じゃなく、「自分」なんじゃないか、ということだ。
若い頃は、何かあれば病院に行けばいい。そう思っていた。
でも60代になって、体の声がはっきり聞こえるようになると、そうもいかなくなる。
定年後の健康は、誰かがなんとかしてくれるものじゃない。自分で作っていくものだ。そう実感している。
「予防しておきたい」気持ちが届かない現実
ある時、股関節と膝に痛みを感じ、町医者を受診した。
レントゲンで「背骨が少し曲がっている」と言われ、専門の整形外科を紹介された。
ところが紹介先の病院では、痛みが出ていないという理由で、「今は診る必要はありません」と門前払いのような対応を受けた。
予防的なリハビリをお願いしたかっただけに、ショックだった。
今思えば、その医師に悪気があったわけではない。
整形外科という現場が、基本的に「症状が出てから対応する」文化なのだろう。
でもこちらは「悪くなる前に動きたい」と思っている。
このすれ違いが、“誰か任せ”ではダメだと気づかせてくれた。
毎日5000歩の散歩が、自分の健康づくりのスタートだった
その経験以来、私は自分の健康は自分で守ろうと決めた。
まず始めたのが、毎日の散歩だった。
最初は5000歩を目安に、近所の田んぼ道を歩いた。
特別なトレーニングではない。
でも、歩くだけで体が軽くなり、頭もスッキリするのがわかる。
2年ほど続けてきて、いまは「これをやらないと落ち着かない」と思えるほど生活に溶け込んでいる。
フルリタイヤ後に始めた「通いながら守る」健康管理
私が歯科の定期検診を始めたのは、ここ2年ほど。
ほぼフルリタイヤしてからだ。
3ヶ月に1回、歯垢除去や歯ぐきの状態をチェックしてもらっている。
特に異常がなくても、
「この部分は汚れが残りやすいですね」
「歯茎は今のところ安定しています」
と、丁寧に説明してくれる。
“予防を前提にした文化”が、歯科にはちゃんとある。
この姿勢に触れるたびに、「自分の健康は自分で守るもの」という意識が自然と強くなる。
また、血圧の検診も3ヶ月に1回受けている。
こちらも、薬を飲むだけで終わらせず、生活習慣の見直しとあわせて管理している。
健康診断は年に1度。数値の上下を見るより、「自分の生活、ちゃんと向き合えているか?」を確認する時間だと思っている。
結局、「自分の体は自分しか守れない」
60代になると、体調は“急に悪くなる”というより、“じわじわと崩れる”ことが多い。
だからこそ、気になったとき、違和感を覚えたとき、小さなサインを見逃さずに行動できるかが大切だ。
整形外科に期待しすぎてガッカリした経験も、
毎日の散歩が習慣になったことも、
歯科や血圧検診を「通いながら守るもの」と考えるようになったのも、
すべては「自分が動くかどうか」にかかっていた。
まとめ:「医者にかかる」より「自分にかかわる」
医者に相談するのはもちろん大切だ。
でも、医療は“最後の手段”でもある。
普段の生活の中で、何を選び、何を習慣にするか――
それが、定年後の健康を大きく左右する。
健康を「保つ」のではなく、健康を「つくる」。
それは、病院の中ではなく、自分の暮らしの中から始まっている。
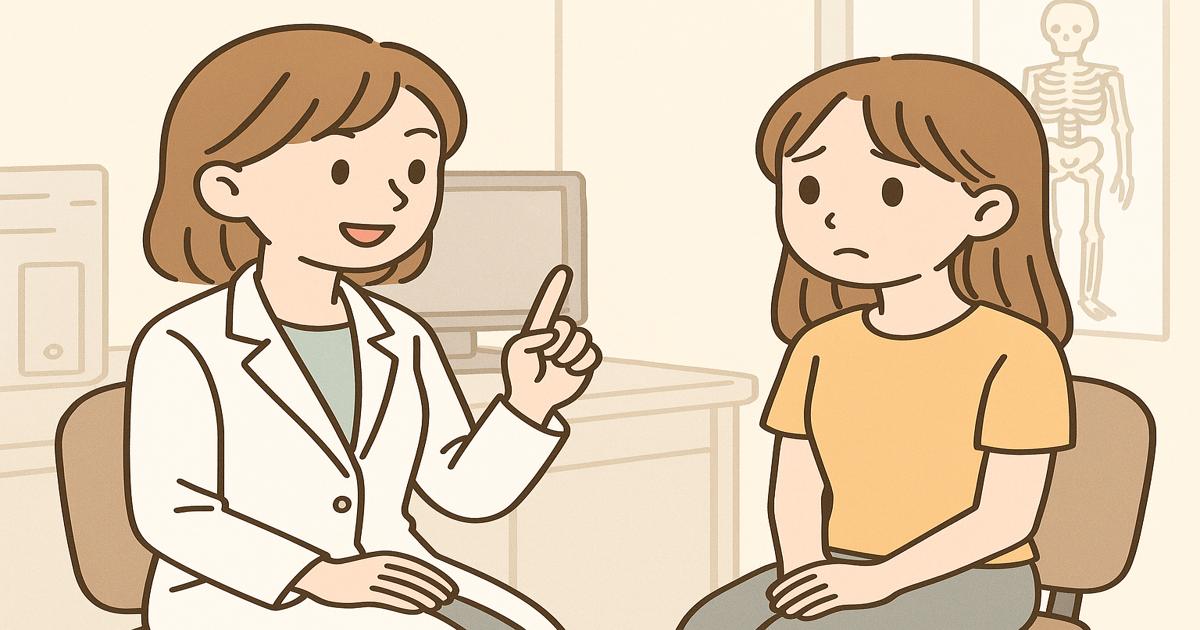


コメント