先日、ある説明会に参加したときのこと。
国勢調査の説明会だったのですが、正直なところ──司会や会議の進め方があまりにも下手だと感じました。
話の流れが定まらず、肝心なところで空気が止まる。
見ていて「私ならこうやるのに」と思う場面が何度もありました。
そのときふと、「会議って、空気の読み方ひとつでこんなに変わるんだな」と気づいたのです。
司会者がどう進めるか、主催者がどうまとめるか、幹事がどう支えるか──。
同じ会議でも、誰がどんな“空気の読み方”をするかで、全体の印象は大きく変わる。
■ 会議のタイプで求められる“空気の読み方”は違う
会議とひとことで言っても、目的はさまざまです。
その目的によって、司会者・主催者・幹事、それぞれに求められる“空気の読み方”が変わります。
私なりに整理してみると、次のようになります。
● 難問解決・企画系の会議
- 目的:新しい発想を出す、停滞を打破する
- 向いている姿勢:主催者・司会者が「あえて空気に流されない姿勢」を持つ。
- ポイント:あえて沈黙を破り、違和感を言葉にしてみる。
こうした場面では、場の空気に流されず、問題の核心を突く一言が大切です。
「今までのやり方で本当にいいのか?」と問いかけることで、会議が動き出すことがあります。
● 実務・報告系の会議
- 目的:進捗確認や課題共有
- 向いている姿勢:幹事・司会者が「空気を読む力」を発揮
- ポイント:参加者の温度を見ながら、丁寧に意見を拾う
こうした会議では、テンポよりも安心感が大切。
空気を読みながら話の流れを整理し、参加者が発言しやすい雰囲気をつくることが成果につながります。
● 意見調整・合意形成の会議
- 目的:異なる意見の整理、納得点の発見
- 向いている姿勢:主催者が「読む」と「読まない」を使い分ける
- ポイント:流れを見つつ、必要な場面では方向を変える勇気を持つ
空気を読みすぎると何も決まらず、読まなすぎると不満が残る。
このタイプの会議こそ、司会や主催の腕が試されるところです。
● 雑談・親睦系の会議
- 目的:関係づくりや雰囲気の維持
- 向いている姿勢:幹事が空気を“味方につける”
- ポイント:和やかさを重視し、場のリズムを大切にする
雑談の中にも大切な情報や信頼関係の芽があります。
このタイプでは、“読む力”が場の雰囲気を作る主役になります。
■ 「読む力」と「読まない勇気」——どちらも必要
空気を読むとは、人の気持ちを察し、場を整える力。
一方、空気を読まないとは、遠慮せずに意見を出し、停滞を打ち破る力。
どちらか一方だけでは、会議は前に進みません。
大切なのは、**“読むか読まないか”ではなく、“いつ、どの程度読むか”**というバランス。
場の性質に合わせて、その都度スイッチを切り替える柔軟さこそ、会議を前に進める力です。
■ 主催・司会・幹事、それぞれの立ち位置
主催者は、目的を決める人。会議の軸をぶらさない責任を持つ。
司会者は、流れをつくる人。会話の方向とテンポを整える役。
幹事は、場を支える人。人の気持ちをつなぎ、空気をやわらげる。
どれも欠かせない役割です。
空気を読むか、読まないか──その選択次第で、場の印象や成果が変わっていくのだと思います。
■ 自分自身を振り返って
私はどちらかというと、顔色をうかがってしまうタイプです。
強く引っ張るような司会はできませんが、
人の話を丁寧に聞き、場を落ち着かせることならできる気がします。
空気を読むことも、立派な力で、
空気を読まないことも、勇気の表れ。
どちらが正しいではなく、場に合わせてどう生かすか。
最近は、そんなふうに思うようになりました。
■ まとめ
会議をうまく進めるコツは、空気を読むことでも、読まないことでもない。
大切なのは、その場の目的に合わせて“空気の読み方”を変えること。
司会者も、主催者も、幹事も。
みんな違う形で会議を支えている。だからこそ、誰か一人では成り立たない。
それぞれが自分らしい“空気の読み方”を持っていれば、場はきっとうまく回る。
最近、そんなふうに感じています。


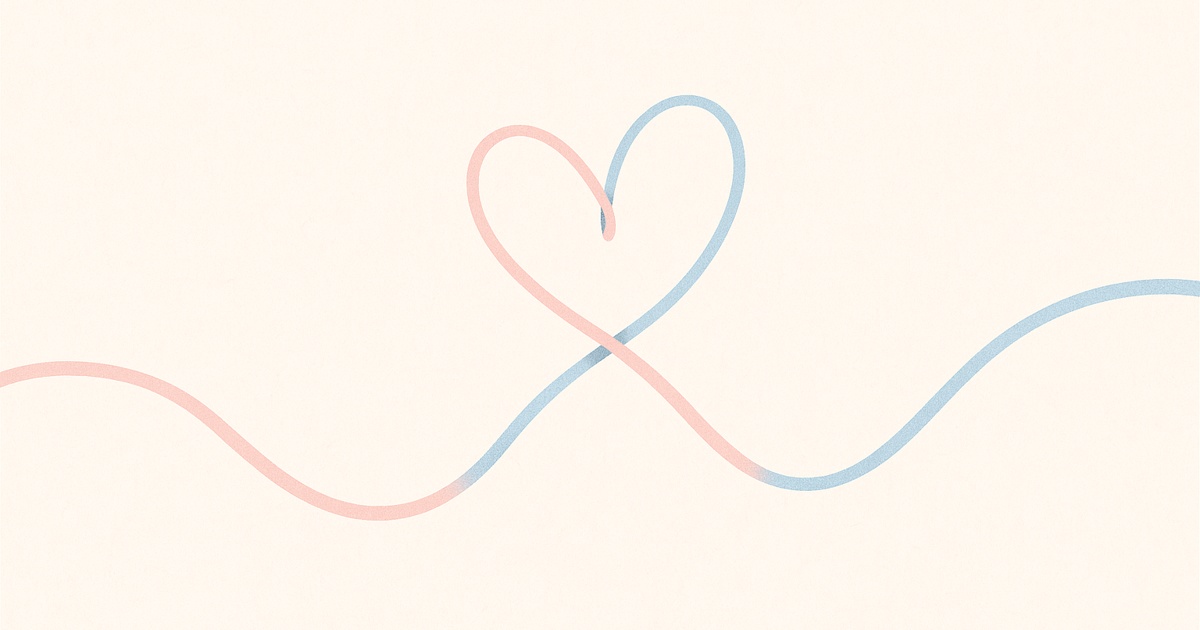
コメント